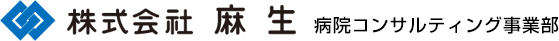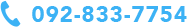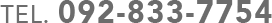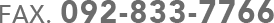在宅事業立ち上げに係る支援の流れ
在宅医療事業の立ち上げは、病院の収益拡大や地域医療への貢献につながる可能性がある一方で、病院内の限られた人的資源を分散させる等のハードル・懸念点があります。より効果的な取り組みとするためには、地域需要の把握、サービス内容の計画立案、スタッフの育成、連携体制の構築、広報活動等、多岐にわたる準備を計画的に推し進めることが重要となります。
また、病院ごとに達成したいテーマ(退院後も安心できる医療提供体制の整備、在宅患者の緊急入院受入による入院患者数の増加、地域包括ケア病棟入院料の施設基準(在宅医療等の実績)の安定的達成等)を念頭に置いた制度設計も必要です。
我々は、病院の機能再編や経営改善の実績に基づき、「既存の医療機能活用」といった視点でも在宅事業の立ち上げをご支援させていただきます。
STEP01
事前調査・市場分析
- 地域における在宅医療の将来需要推計を算出する
- 内部環境分析(:診療実績や職員配置状況の分析・病院職員へのヒアリング等)及び外部環境分析(:地域における既存の在宅医療提供状況の確認等)を実施する
⇒地域における在宅医療事業展開の道筋(:強みとなりうるポイントや在宅医療の対象となりうる患者スケールの概況等)について整理する - 中心となって推進し得る人材の有無(訪問診療の場合は医師等)
-
ポイント:適正人材の有無
何よりも中心となって事業を推進し得る人材の有無は、事業開始可否の判断に大きな影響を及ぼします。
-
ポイント:地域ニーズとの適合性
在宅事業が病院にとって有効な事業となり得るかは、地域ニーズ及び既存病院との診療上の親和性の有無に大きく左右されます。 在宅事業の中でも、いずれの領域(訪問診療・介護・リハビリ等)であれば強みを活かすことが出来るか、実現性があるかについても判断していくことが重要になります。
STEP02
計画立案(事業構想の具体化)
- STEP1で得られた分析結果から、適切と思しき在宅医療事業の形態(:訪問診療/訪問看護ステーション/訪問リハビリテーション等)やターゲット患者層(:高齢者/末期がん患者/慢性疾患の患者等)を決定する
※新規に立ち上げる在宅事業が「どういった状態・範囲に対応することを目指すのか」事業構想を具体化する - 地域需要と院内の人的資源等に応じた事業規模を明確化する
- 必要な費用を見積もり、費用に見合う収入目標等を策定する
※収入目標を達成しうる利用者数・単価水準も可視化する - 必要機器等への投資や職員採用~研修の実施、地域の医療機関等との連携、院内診療報酬請求体制の整備、広報戦略の方針について整理する
-
ポイント:収益性の確保
在宅医療による収入は入院医療と比較して低いケースが多く、収益性を確保するためには、効率的な訪問スケジュールや、診療報酬の最大化を目指す戦略を立てる必要があります。また、どういう事業規模を目指すのか(開始~将来)の想定も重要となります。
-
ポイント:コスト管理
在宅医療に必要なスタッフ、機器、車両、時間管理を考慮した上で、コストを可能な限り抑えた計画を策定する必要があります。
-
ポイント:目標値の設定
「客観的に実現可能であり、かつ、収支上達成すべき目標値」は、院内のみの視点では設定に難航するケースが散見されます。また、病院本体との相乗効果も想定する必要があります。第三者の介入により、各関係者が納得感をもって進められる可能性が高まると考えます。
STEP03
事業開始に向けた準備~事業運営開始
- STEP2で立案した計画に則り準備を進め、事業を運営開始する
-
ポイント
事業開始に向けては、各種届出対応および基準に則った運用面の整備が必要となります。私たちは複数の在宅医療事業立ち上げに係る支援実績や関連医療機関での実際の運用方法等に基づき、実運用に沿った現実的な検討・提案させていただきます。
STEP04
事業開始後の運営体制の見直し(継続)
- 他院の詳細な運用方法や在宅医療を受けた患者・患者家族からのフィードバックを定期的に収集することで、サービスの改善に役立てる
- ニーズや実運用に応じたサービス内容の拡大や効率化について検討する
-
ポイント:患者確保の経路拡充
事業開始後、利用者増加に向けたアプローチは重点的に実施していく必要があります、アプローチ先の選定を含め支援を継続して実施いたします。
-
ポイント:継続的な改善と評価
在宅医療事業は、患者数やスタッフ1人あたりの生産性、収支状況を定期的に評価し、改善を続けることが求められます。スタッフの負担軽減や効率化の視点も重要となります。
-
ポイント:サービスの拡充と多様化
ニーズに応じて、関連する新たなサービスを追加することも検討する余地があります。
【(参考)病院が各在宅事業立ち上げ検討に至る一般的な理由・背景(例)】
- 訪問診療
- 地域住民の高齢化が進行することによる在宅ニーズの増大、地域開業医の高齢化、地域包括ケア病棟の安定的な要件クリアの必要性、総合診療科医師の存在
- 訪問看護(ステーション)
- 訪問診療との一体的なサービスの展開可能性、病院をバックボーンとする質の高いサービスの提供可能性、周辺看護ステーションのサービス提供範囲の制限(時間・対象疾患等)
支援実績
【A病院:在宅医療事業立ち上げ検討時の状況】
- 地域住民や地域開業医の高齢化が進行しており、地域との関係性をさらに強固なものとする視点の取り組みが必要な状況。医師の体制は変わらないものの、患者数は年々減少傾向。
- 地域包括ケア病棟を有しており、地域包括ケア病棟入院料の施設基準である「訪問診療の件数」について安定的な達成が望ましい状況。
【A病院:在宅医療事業に係る主目標】
- 訪問診療
- 地域内でトップクラスの訪問診療対応(在宅療養支援病院⇒単独型へ)
- 訪問看護
- 訪問診療との連携・一体的なサービス提供の実現(認定なし⇒訪問看護ステーション化)
- その他
- 上記サービスとの相乗的な効果を鑑み、「訪問リハビリ」等の展開も検討

- 在宅療養支援病院の認定や訪問看護ステーションの立ち上げ・・・
- 提案から約1年足らずで実行!
2~3年目には目標稼働に到達!
- 地域包括ケア病棟入院料の「訪問診療の件数」に係る基準・・・
- 達成!(継続中)
- 病院本体の地域での認知度向上・入院患者数増加に間接的に寄与・・・
- 達成!(継続中)